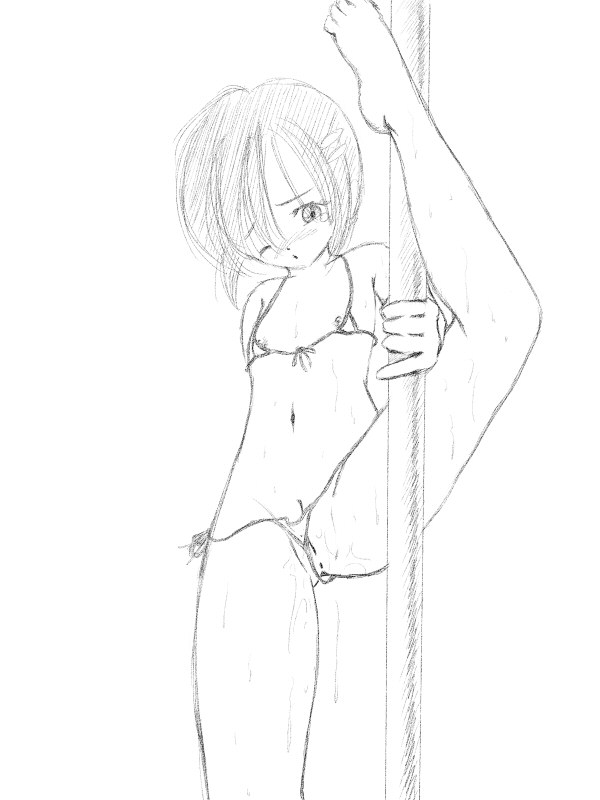 杏の脚が大きく振り上げられた。
杏の脚が大きく振り上げられた。天井を打つほどの角度で片脚が持ち上がり、足首をちょこんと曲げて銀のポールにからみつく。
だぶだぶだったビキニの下が大きくたわみ、男子たちからひゅうっという歓声が上がる。
不来方 杏(こずかた
あんず)が職員室に呼び出されたとき、生徒指導担当の女教師は眉を吊り上げて彼女を見た。
もともと気の弱い杏は、その視線を受けてびくりと身を竦める。
「――す、すいません……」
職員室に来るまでにも、学園内のもろもろの設備を通過してこなければならないため、杏の顔は激しく上気し、膝はわずかに震えていた。
スカートをぎゅっと握り締めているのは、絶頂寸前まで高まったことを隠すためだ。
女教師はその杏の様子を見て、まあいいわ、と言ってテーブルの上に一着の衣装を出す。
「―――」
それを見て杏は焦りの色を浮かべた。
それは学園指定のチアリーディング衣装であり、全体的に非常に薄く活動的なデザインである。
例に漏れず、この衣装にも女生徒を辱めるような加工が施されている。
それは胸の先端が当たる部分で、そこに極細の繊毛が植えつけられており、僅かな動きでも、その繊毛がブラシのように乙女の胸の突起をこするようにできているのだ。
その痒みともくすぐりともつかぬ刺激は巧みに計算されており、チアの動きどころか、普通に着て歩いているだけでも、一瞬たりとその刺激を無視することはできない。
だが、女教師の手に持つそれは違っていた。
繊毛の部分にジェルのようなものが塗られているのだ。
女教師はチア衣装を裏返し、そのべとべとした緑色のジェルを杏に見せる。
「これは、あなたのチア衣装に間違いないわね?
不来方
杏さん?」
「は、はい……」
「こんなものを塗って繊毛の刺激を弱めようなんて、なんて姑息なことを考えるのかしら。
この繊毛はね、貴女たちが女性としての美しさを十分発揮できるように考えられた仕組みなのよ」
「あ、あの、それは……」
そのジェルは杏が塗ったものではない。
ウサギのように気が弱く、引っ込み思案な杏に、そんな小細工をする勇気などあるわけがないのだ。
そのジェルの正体は、寮内の浴場で見られる催淫シャンプーである。
彼女がチアの衣装に着替えようとしたとき、そのシャンプーが乳首の部分にべったりと塗られているのを見つけた。
おそらくは男子のイタズラだと思ったが、教師に言い出すことができず、そのままチアの授業を受けたのだ。
だが幸か不幸か、その催淫シャンプーは確かに乳首に熱っぽさを与えたものの、ブラシで掻きみだされる刺激が抑えられたことの方が大きく、普段は高いジャンプや大きなターンごとに耐え難い快感が襲うチアの授業も、比較的平穏にやり終えることができていた。
だが、それでこの件が終わりなどと思うのは、考えが甘すぎたと言うべきだろう。
杏がそれは、と抗弁しかけたのを、女教師の強い眼差しが押し止める。
「それは?」
「……い、いえ……何でも」
「いい?
あなたはこの件で3つ、あるいは4つの校則を犯しています。
制服の無断改造、校舎内への私物持ち込み、この場合はこのジェルね。
授業を真面目に受けなかったこと等ね。
反省はしていますか?」
「――は、はい、反省しています」
もはや、何を言っても通じるような場所でないことは明らかだった。
元は男子のイタズラのせいでこうなったことを悔しく思いながらも、ぎゅっと唇を噛んでただ頭を下げた。
「そう?
では、どうしてこんなことをしたのか理由を聞きましょうか?」
「そ、それは、あの……ち、乳首がこすれるのが、い、いやで」
「もっと正確に言いなさい、擦れて乳首がどうなるのが嫌なの?」
「あ、あの、お、大きくなったり、赤くなったり、き、気持ちよくなったり、す、するので」
「気持ちいいのがどうして嫌なの?」
「そ、その……き、気持ち、よく、なってるところを、み、見られるのが、恥ずかしくて……」
「でも、気持ちよくなっていることがどうして男子にわかるの?」
「あ、あの……」
「答えなさい」
「そ、それは……く、口元がゆるんだり、よだれ…をたらしちゃったり、足がふるえちゃったり、す、するからです」
「なるほど、繊毛に乳首が擦れて、乳首が大きく赤く膨れ上がって、それがさらにごしごしと繊毛に刺激を受けて、そうなると気持ちよくなってにやけた顔になって、足腰ガクガクになってヨダレを垂らすあられもない姿になるから、それを見られるのが嫌、こういうことなのね?」
「――は、はい」
その淫らがましく責めつける言葉に、杏の頬は果物のように赤くなり、恥ずかしさで鼓動も高まってくる。
元々、クラスメートの中でも特に羞恥心が強く、わずかに肌が晒されるだけでも必死にそれを隠そうとしたり、男子の淫猥な言葉にかたくなに耳を塞ごうとする、そんな少女なのだ。
その性質は逃避、閉息、そして隠忍。籠の中の小さな鳥。
「杏さん、あなたには普段からそのような傾向があるわね。
女性として恥ずかしいという感情を持つのは大事なことだけれど、貴女は少し内向的過ぎるのじゃなくて?」
「は、はい……」
「わかりました。
では貴女には特別プログラムを命じます。
明日の放課後、音楽室まで来るように」
「――え」
男子に逆らったり、校則に従わなかった女子が「反省」を命じられることはよくある。
だが特別プログラムというのは何だろうか。
「いい?
あなたのやったことは、本来は反省室行きになっても仕方のないことなのよ?
ですが、あなたは普段から男子の言うことも従順に聞くし、成績も優秀なので、今回は反省より、あなたのその恥ずかしがり屋の気質を治すことを優先することにしました」
「は、はい……」
「わかりましたね?
では帰りなさい」
杏が反省室を出ていくとき、廊下にいた10人ほどの男子たちが、にやにやと笑いながらほうぼうに散っていった。
明らかに何かを楽しみにしているようなその後ろ姿を見て、杏は不安な気持ちに駆られる。
杏はその特別プログラムとやらのことを考えずにはいられなかったが、廊下の渡り棒や寮での催淫剤尽くしにより、その疑念を長く考え続けることはほとんどできなかった。
※
夕日が赤く染まり始めるころ、『特殊視聴室』というプレートが下げられた部屋に杏はいた。
椅子に座るその前には、一台のテレビが置かれている。
女教師はテレビの脇に立って、機器をいじっている。
「さあ杏さん、あなたにはこれからDVDを視聴してもらいます。
20分ほどの短い映像だから、よく見て、内容をしっかりと覚えるようにね」
「は、はい」
映像が始まる。
外人の女性が映っていた。
一糸まとわぬ、全裸の姿である。
「……っ!」
いきなり裸の女性が現れたことに面食らったが、女教師がしっかりと杏を見据えているため、映像から目を背けるわけにはいかなかった。
映像の中の女性は20代半ばというところだろうか、スタイルがよく、豊満なバストと引き締まったウエストを持ち、どこか筋肉質な白人の女性だった。
髪は見事なブロンドである。
その女性は、足元に落ちていたビキニの水着を身につける。
ごく普通の白い水着だ。
なぜ、裸で出てきたのにわざわざ水着を着るのだろう? と、杏は少し違和感を覚える。
女性の後ろには、天井まで伸びる銀色のポールがあった。
手で握れるほどの太さの金属製のポールである。
よく見れば、女性の立っていた場所は何かのステージのようだった。
床には電飾が散らされており、ポールのほうに歩みよる女性を、ピンク色のスポットライトが照らし出す。
BGMが静かに流れ出す。
(こ……これって……)
そしてそれは始まった。
むっちりと張り詰めた太腿がポールに絡みつき、たわわなバストがゆさゆさと揺れ、妖艶な眼差しが画面に投げられる。
いわゆるポールダンスと呼ばれるものだ。
ポールダンスの特色としては、ポールを男性器に見立てての卑猥な振り付けはもちろんのこと、やはりポールを利用したアクロバティックな動きがある。
ポールに背中を預けて大きく倒れこんだり、高い位置によじ登ったまま、手や太腿でポールに掴まってくるくると降りてくる、という動きは迫力がある。
だが、そのDVDの中の振り付けは少し変わっていた。
スクワットのような上下運動の際に、本来は腰をポールから浮かすはずなのだが、その映像ではいちいち局部を密着させている。
まるでその部分を掻いているような、いかがわしい動きだ。
脚を大きく菱形に開きながらの屈伸運動でも、股間をごりごりとポールに押し付けている。
ポールを太腿で挟んで上下したり、バストの先端をちろちろとポールに当てたり、それは本来のポールダンスを知っている人間には少し違和感のある振り付けであったけれども、杏は実際にポールダンスを見ること自体初めてであったし、それは十分すぎるほどになまめかしくいやらしい動きだったので、見ながらも背中に汗をかくほど体温が上がり、顔は湯気を放つほど真赤になってしまっている。
なんだが頭がぼうっとしてくる。
(こ、これが……特別プログラム……なの?)
やがて映像は終わる。
黒い画面になったかと思うと、女教師はメニュー画面を操作し、DVD内の別のトラックを再生する。
「さあ、もう一度よ。
今度は異なる4つのアングルから撮影したものです」
「……?」
先ほどと同じ女性である。
一糸まとわぬ姿で現れ、足元の白いビキニを身につける。
違うのは、画面が4つに分割されており、ひとつには最初と同じ正面からの映像、ふたつ目は右側から撮影した映像、3つ目は左側から、そして4つ目は後方から撮影された映像である、という点だけだった。
2度目でもやはり恥ずかしいことに違いはない。
杏は早くこの場から逃げ出したい思いに駆られつつ、ヒザの上で手をぎゅっと握って、ただただそのビデオを見続けた。
2回目の視聴が終わった。
ダンスは1回20分ほどであるから、都合40分が経過したことになる。
「視聴は以上です」
「は、はあ……」
「さあ、杏さん、振り付けについては『理解できました』ね?
では服を全て脱ぎなさい」
「えっ……」
「早くなさい」
有無を言わせぬ口調だった。
何故脱ぐのか、そんなことを質問する権利はない。
杏はか細い声で、はい、とだけ言って、しゅるりとスカーフを外し、小さな衣擦れの音をさせて服を脱いでいく。
このときいつもの杏ならば、まだ人前で服を脱ぐ恥ずかしさに身悶えしたであろうけれど、そのときは女教師の言葉に素直に応じていた。
自分の身に起こりつつある変化について、まだ杏は気付いていない。
女教師は時計をちらりと見て、杏が脱ぐのを待った。
「ぬ……脱ぎました」
「よろしい。
では隣の音楽室へ移動しましょう」
「……」
果たして、そこには既に男子たちがいた。
20、いや、40人はいるだろうか。
物音一つさせずに、みな同じようににやにやと笑ったまま、音楽室の外周にぐるりと座っている。
そして音楽室の中央には、いつのまに設置されたのか、銀色のポールがある。
女教師が男子を見渡して、言った。
「観覧希望者はこれで全員かしら?」
「はーい先生、これで全員です」
「お、始まるの?」
「それにしても随分集まったなあ」
「そりゃそうだろ、何せあの杏ちゃんが――」
女教師の声を皮切りに、いっせいにざわざわと話し始める。
(だ……男子が……こんなにいっぱい……)
杏はこれから行われることを何となく悟った。
恥ずかしさのあまり頭の中がぐちゃぐちゃになっている。
そして、ようやく自分がまったくの裸のまま男子の注視を浴びていることに気付いて、不意にその場にうずくまりそうになる。
いつものように両手で身体を抱え込み、リスのように小さくなってしまおうと。
だが、体が動かない。
女教師に促されるまま、すたすたと音楽室の中央、ポールのそばまで歩いていく。
「さあ皆さん、これより杏さんのポールダンス・ショーを始めます。
これはあくまで授業の一環ですから、ダンス中に杏さんに触れたり、何か特別なことを要求するのは禁止します。
いつもと同じですね」
「はーい」
「うぉーい」
男子がめいめいに答える。
よく見れば杏の足元にはビキニの衣装が置かれていた。
それはしかし、先ほどの映像に映っていたようなしっかりとした水着ではない。
いわゆるマイクロビキニと呼ばれるもので、バストを隠す布地はギターのピックほど。
股間の布も同程度しかなく、きわめて薄い。
杏の手が勝手に動き、そのビキニをつまみ上げる。
(……!?
や、やだ……こんな水着、こんなの……は、裸より、恥ずかしい……のに……)
それをてきぱきと身につけていく。
布地の小ささよりも、それはそもそも、杏の体型に対して少し大きいようだった。
ヒモでしかない肩周りや腰周りの部分はだらしなくたるんでおり、あろうことか、胸の先端を隠す布地もぶかぶかに浮いて、股間の布地も完全にアソコから離れていた。
もはやそれはまったく身体に密着しておらず、布の隙間から可憐な部分が露出しているのが明らかだった。
杏はようやく自身に起こっていることを自覚した。
身体が命令を聞いてくれない。
勝手に動き、勝手にこの破廉恥きわまるマイクロビキニを着て、そして勝手に振り向き、ポールへと歩いていく。
意識だけははっきりとしているのに、首から下はまるで彼女の自由にならない。
胸の先端にかろうじて触れてるだけのビキニの質感も、音楽室の床の冷たい感触も伝わるというのに。
これこそは「P・M・H」と呼ばれる特殊催眠である。
この催眠の骨子は「運動野の支配」「特定情報の焼き付け的記憶」「条件付けによる催眠状態への移行」の3つ。
P・M・Hとはその機能の頭文字だ。
つまりは他人の動きを数十分に渡って完全に記憶し、その動きをトレースする催眠。
先ほど杏がDVDを見ていた特殊視聴室、あれは「特殊なものを見る部屋」ではなく「特殊なやり方で物を見せる部屋」なのである。
映像そのものへのサブリミナル。
可聴域を超えた重低音。
特殊な薬剤の散布などなど、あらゆる方法で杏は深い催眠状態に置かれていた。
今や杏は、先ほどのポールダンスの振り付けを踏襲するだけのマシーンと化している。
先ほどと同じBGMが流れ出した。
その途端、男子たちがわっと色めきだって、ざざっとポールの周りに集まってくる。
「あ……あああっ」
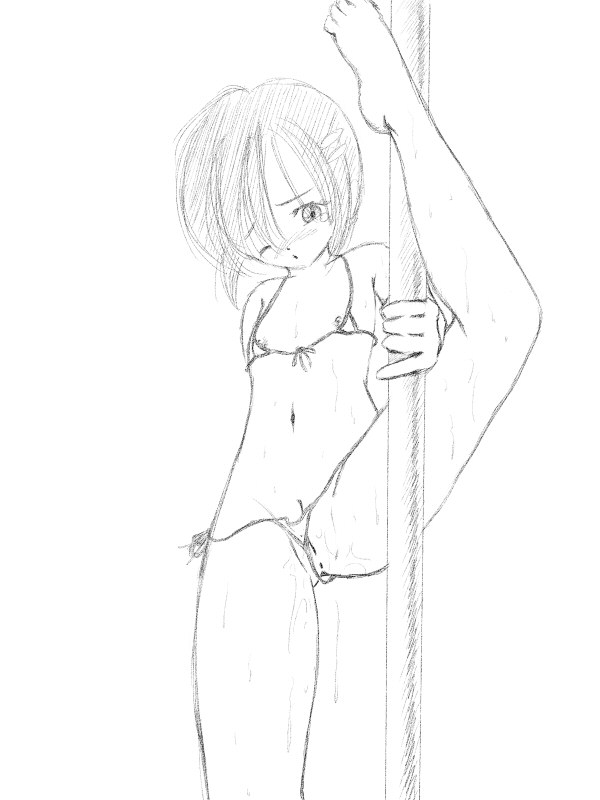 杏の脚が大きく振り上げられた。
杏の脚が大きく振り上げられた。
天井を打つほどの角度で片脚が持ち上がり、足首をちょこんと曲げて銀のポールにからみつく。
だぶだぶだったビキニの下が大きくたわみ、男子たちからひゅうっという歓声が上がる。
「おおー大胆!」
「杏ちゃんかわいー!」
「い……嫌っ、嫌なのに……」
この催眠は、顔の表情筋、および舌の筋肉や肺の横隔膜、その他内臓器官の働きまでは支配しない。
よって、声を出そうと思えば出せる。
しかし、声を出せることが少女たちをさらなる羞恥に追い落とすことなど、この時の杏には考える余裕がない。
もう自分の意思ではどうにもならなかった。
その少女らしさを備えた細い四肢が、蛇が柱に巻きつくようになまめかしい動きで踊る。
関節が溶けてなくなったかのような柔軟性と、バネ仕掛けのような鋭い瞬発力。
そして音楽に合わせて踊るリズム感。
かろうじて身体に張り付いている、といった程度のマイクロビキニが、その大きな動きに耐えかねて今にもずり落ちそうになる。
「ああっ……だっ……だめ、見えちゃうっ!」
杏がそう思うのとは裏腹に、ポールに背中を預けたまま両足を思い切り開いて見せたり、そのままかなりの速さで上下に身体を揺さぶったりと、わざと恥ずかしいポイントを見せ付けるかのような振り付けである。
マイクロビキニは風に吹かれる旗のように面白いほど動き回り、杏の恥ずかしがりやな性格を象徴するように閉じられた割れ目も、恥ずかしさを溜め込んでぷっくりと膨らむ乳首も、ちらちらとこぼれて男子の目に晒される。
杏の額には玉の汗が浮かび、恥ずかしさのあまり歯の根が合わなくなっていた。
「せんせーい、ライトの映えが悪いですよー」
「あら、本当ね。
オイルを塗ってあげましょうね」
何人かの男子が、ペンキ缶のようなものを持って立ち上がる。
中身はどろりとした飴色の液体。
そして女教師にその缶と、T字型の刷毛を渡す。
(……な、なにを……?)
女教師は缶の中身をたっぷりと刷毛にひたし、とぷりっ、とそれを杏の背中に下ろす。
「ひゃうっ……」
ひやりとした感触に声が漏れる。
ポールそれ自体を愛撫するようにくねくねと胴をこすりつける杏の身体を、刷毛が何かの舌のように動く。
「はっ……あぁっ、……ひ、ふっ……」
女教師はポールダンスの振り付けを完全に把握しているらしく、腋を上げれば腋の下を、顔を上げれば喉を、そして腰のくねるに合わせてわき腹にオイルを塗りたくっていく。
そしてひとたび両足を開けば、その桃色にほてったウチモモ、そして大開になってふるふると震える秘部を刷毛がなぞっていく。
「あああっ……ひぐっ……ふっ、ふああっ、だめえっ!」
少女の初々しさを備えた秘唇を、刷毛がちろちろとなぞると、身もだえするかのように割れ目そのものが震えて、瞬間、その内側に燃え盛るような赤色が除く。
「おおっ、割れ目がぱっくり開きそうだねー」
「杏ちゃーん、それは気持ちよくなるためにやってるんじゃないよー」
男子のはやし立てる声に耳まで赤くなりながら、杏はどうすることもできずにその刷毛の拷問に耐えるしかなかった。
それは水アメをかけながら火に炙られる、哀れな子豚のような姿だった。
全身をてろてろに塗らすオイルがライトにきらめき、まるで杏そのものが熟れた果物になったかのような眺めである。
口唇と秘唇は真赤に染まりつつあり、その粘膜の変化は彼女の内面が燃え上がりつつあることを示していた。
変化は徐々に現れてきた。
恥ずかしさのためだけではなく、オイルが塗られた部分が熱っぽく火照り始めているのだ。
わき腹をポールにこすりつけるような振り付け、そのとき、ポールに電気でも流れているかのような、痺れるような感覚が走る。
「――ふぅあああっ!!」
「どう?
この催淫オイル、塗られた部分が気持ちよくてたまらないでしょう?」
聖女学園で使用される媚薬には様々な種類があるが、このオイルは特に感覚神経に強く作用する。
オイルが塗られた場所は、そこに与えられた刺激がすべて快感様に変化し、その過敏さが数倍に跳ね上がる。
背中であろうと腕であろうと、すでに杏の全身は膣内粘膜のような「快感を得るためだけの部位」に変化している。
ましてや元よりそうである秘唇などは一層過激なことになっており、何もしなくてもジンジンと勝手に興奮しだしている。
「あ……あああ……こ、こんな、こんなぁぁ……」
「あらあら、杏さん、そんなにポールが気持ちいいの?
そこは背中よ?」
まるで猫が背中をかくような、ゴリゴリとポールに背骨を押し付ける振り付け、それは極上のマッサージのような、耐え難いほど甘美な刺激に感じられた。
わき腹を擦ればわき腹が、顔を押し付ければ顔が気持ちよくてたまらない。
杏が記憶しているこの振り付けは、身体にこのオイルを塗られることまでしっかりと計算に入っているらしい。
(こ、これ……き、気持ちいいよおっ……)
男子の注視を浴びていることすら忘れかけるほどの甘美な刺激、ましてやそれは背中や腹なのだ。
今の自分の局部に何かが触れたら、という考えが杏の頭をよぎった瞬間、女教師が絶望的なことを言った。
「さあみんな、杏さんのダンスがこれからもっと素敵になるから、しっかり見てあげてね」
女教師がゆっくり近づいてきて、ポールのかなり高い部分に手を伸ばす。
するとカチリとスイッチを入れる音がして、フォーンという、ウーファーの様な重低音が響いた。
「――!」
杏はポールを両手で掴み、馬のようにお尻を振っていた。
その手に、びりびりと激しい振動が伝わってくる。
(――こ、これ、このポールって)
杏は理解した。
このポール自体が、強力なバイブレーター機能を備えている――。
杏の腰が前方へとスライドし、がばっ、と両足が開かれた。
空気イスのような姿勢でポールを挟み込むように構え、つかづ離れずの距離で、ポールを今まさに挟み込もうとするかのように両足を揺さぶる。
「あああぁっ、だ、だめっ!!」
その距離はわずか1センチほど、ポール全体の微弱な振動が空気を通して伝わってくる。
びりびりという空気の震えが皮膚に伝わり、オイルで活性化された皮膚がぞくぞくっと甘美な予感に戦慄する。
「杏ちゃーん、何がだめなのかなー」
「うひゃー、杏ちゃんのアソコ、ピンクどころか真っ赤になっちゃってるよ」
「あんなに充血したアソコでバイブポールを挟もうなんて勇気あるねー」
男子がこころもち身を乗り出し、杏の可憐な花びらがポールにキスをする瞬間を、杏の全ての理性が吹き飛んで歓喜の絶叫をあげる瞬間をにやにやと待ち受ける。
そしてひと際大きく股が開かれた後、その両足が、抱きしめるようにポールを包み込むと同時に、過敏の極みに達した秘部がポールの振動を受け止めた。
「ふああああああああっっ!!! あ゛あ゛あああああっ」
一秒以下の速度で絶頂が走りぬけた。
全身が火薬のようにはじけ、喉の奥から搾り出す甘い叫びが窓ガラスを奮わせる。
膣孔がぎゅっとすぼまるとともに、しとどに溢れていた愛液が音を立ててはじけた。
「あ゛あ゛あうううふわあっっ!! い゛うああああっ!!!」
雷鳴のような絶頂が身体の芯を往復している。
声をまったく抑えることができず、いまだかつて杏が夢にも出したことのない、獣の叫びがこだまする。
「おおっとお、杏ちゃんの本気声でたねー」
「うひゃー、みっともない叫び方だなー」
「潮まで吹いちゃって、杏ちゃんってそんなはしたないイキ方するんだねー」
ぶ ぶ ぶ ぶ ぶ ぶ
愛液で塗れた秘部がバイブポールと触れあい、そんな卑猥な音を立てる。どろどろに塗れた陰唇がはじかれる音だ。
脳の奥で閃光が明滅する。だが、完全催眠はそんな杏の身体をも支配していた。
腰を左右に揺らしながら、バイブポールに執拗に局部をこすり付ける動き、脚を大きく斜めに振り上げて、局部をポールに密着したままその周囲を一回りする動き。
つつましげな形をした少女の秘裂が、カエルが口を開いたように引き歪んだ形になっている。
体液に濡れそぼったマイクロビキニは腿のあたりまでずり落ち、何かを隠すという役目を完全に失っていた。
もちろん杏にはそれを直すことなどできない。
歩くどころか指一本動かせないほどの快感が襲っているのに、それでも身体が動く。
淫らがましくもさらなる快感を得ようとするかのような、淫乱放蕩きわまる踊り。
「あ゛……、あがああぁっ……も、もうイキたくないの、にぃ……」
「あらあら、なんてだらしないアヘ顔なんでしょう。
舌がはみ出しちゃってるわよ」
女教師は呆れたような声でそう言い、肩をすくめる。
「まだまだよ、これから一番の見せ場が残ってるのよ?」
「は……あぁ……そ、そん……なあぁ」
それはあまりに絶望的な言葉だった。
いっそ気を失ってしまえば楽かとも思ったが、催眠のためだろうか、失神することはおろか、感覚を遮断することもできなかった。
恥ずかしさも気持ちよさも、だんだんと大きくなる一方だった。
杏は、のけぞるような体勢でなまめかしく上体をくねらせている。
自分の小さな胸を自分で狂おしそうに揉みしだき、催淫オイルで充血した乳首をぎゅっとひねる。
もはや痛みなどは巨大な快楽の一部でしかなかった。
そんな杏の視線の先で、女教師がポールに何かを被せていた。
それは茶色い筒状の布で、どうやら何かの毛皮のようである。
「ふふっ、杏さん、これが何だかわかる?」
「わ……わかり、まひぇえん……」
「これはね、ミンクの毛皮よ。
もともとはイヌイットの男が凍傷を防ぐためにアソコに被せたものなの。
それは帽子状ですけど、これは筒状にしてあります。
そして、これは性の道具としても最高なの。
ヨーロッパの淑女たちの間でこれを使ったセックスが流行したとき、どんなに貞淑な乙女であってもこれで突かれれば歓喜に泣き叫び、日が沈んでから夜が明けるまで果てしなくヨガリ狂い続けたそうよ」
「ひ……い、いゃぁ……そん……なの……」
ミンクの筒はするするとポールを下りてきて、やがて、杏の股間に接する高さで結わえ付けられる。
絶妙の硬さと細さを備えた数万の毛が、じゅりっ、と杏の股間に擦れた。
「う゛あああきゃあはあぁ! あ゛あ゛ぅあ゛あぁ!!!」
もはや人間の叫びとは言えなかった。
雌の野生をむき出しにした、叫ぶではなく吼えるような声。
目が完全に白目を剥いて舌は限界まで飛び出し、涙を流して乱れ狂う。
「ふうああああぁぁっ、ひゃふへああああぁぁ! だめへええええぇっぐう゛うううぅっ」
極細でありながら硬いシンを持つミンクの毛が、あらゆる襞の奥に、淫核を保護する包皮の中にまでずりずりと侵入し、無数の生き物のようにあらゆる動きで暴れまわる。
感覚神経をすべてほじくり返されるような異次元の快楽。
絶頂が持続性を得たかのように続けざまに押し寄せてくる。
「杏さん、とっても気持ちよさそうね。
みんなに見られてるのがいいの?
男の子に見られながら、ミンクの毛で股間じょりじょりされてイっちゃうの?」
女教師が意地悪くそう聞いてくるのも耳に入っていなかった。
杏は電極の刺激を受けて悶える実験動物のように、快感を与えられるだけの生き物になっていた。
「曲が終わるまであと7分ほどだけど、それまでにあと10回ぐらいはイけそうね。
あらあら、いろんなお汁垂れ流しにしちゃってだらしないわねえ。
さあ、男子もしっかり見てあげてね」
男子たちのはやし立てる声に、女教師の艶かしいささやき。
杏のダンスは永遠かと思われるほどに続き、何度も何度も絶頂が駆け抜け、杏はそのたびに喉を張り裂くように鳴いた。
ミンクの毛皮が愛液をかき分けて果てしない蹂躙を続け、粘性を帯びたドロドロの汁が、その足元に水溜りのように広がっていた。
※
このポールダンス以降、杏はしばらくの間きわめて従順になり、男子のどんなに恥ずかしい要求にも、ダンス……と一言ささやくだけで応じたという。
しかし、恥ずかしがり屋の性格だけはなかなか改善せず、その後もたびたび女教師や男子から、恥ずかしくて耐えられないような課題を要求され続けるのであった――。
文章:ばろさん